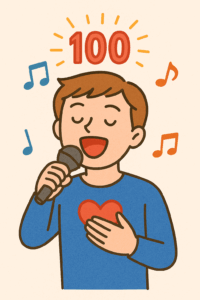高音が出ない原因と解決法|輪状甲状筋の働きを知って声を変えるボイトレ法
はじめに
「高い声が思うように出ない」「歌うと喉がすぐ疲れる」
そんな悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。
高音発声を理解するカギとなるのが、喉の中にある 輪状甲状筋(りんじょうこうじょうきん)。
今回は、この筋肉の働きと高音発声の仕組みを分かりやすく解説し、日常の練習で役立つボイトレ法もご紹介します。
高音はどうやって出ている?
高音を出すとき、声帯は「伸びて・細くなる」ことで振動数が増え、音が高くなります。
このとき声帯を伸ばす役割を担うのが 輪状甲状筋 です。
声帯はギターやベースの弦と似ています。
- 太い弦 → 低い音
- 細い弦 → 高い音
声帯も同じように、細く伸びることで高音を生み出しているのです。
声帯が振動する仕組みを簡単に言うと、息の力で声帯がパタパタと開いたり閉じたりすることで音が生まれます。
たとえば、草笛の音にたとえると分かりやすいです。
草の葉に息を吹きかけると、葉っぱが震えて音が出ますよね。
同じように、私たちの声帯も息の流れによって震え、その振動が声となって響いていくのです。
このとき、声帯はただ勝手に動いているのではなく、息の圧力で開き、空気の流れの力で閉じるというサイクルを繰り返しています。
そして高い声を出すときは、このサイクルをスムーズにするために 輪状甲状筋(りんじょうこうじょうきん) が声帯を「細く・ピンと張る」ように助けています。
ギターの弦を強く張ると高い音が鳴るのと同じで、この筋肉があるから高音が出やすくなるのです。
輪状甲状筋を使わないとどうなる?
高音を避けていると、この筋肉が使われなくなり、
「高音が出しにくい → 出さない → さらに出なくなる」
という悪循環が生まれます。
また、喉の筋肉を使わないことは 嚥下機能(飲み込む力) の低下にもつながり、健康面でもリスクがあります。
若い方でも油断は禁物で、喉仏の位置は30代から徐々に下がるといわれています。
さらに、高音を出すための筋肉(輪状甲状筋)と低音を支える筋肉(甲状披裂筋など)のバランスが崩れると、声の安定感や響きに影響が出やすくなります。
高音トレーニングの基本ステップ
高音を鍛えるには、輪状甲状筋を刺激するシンプルな練習が効果的です。
練習例|地声から裏声への切り替えトレーニング
① 声だけで行う方法
- 発声例:「うーいー」
- 低い音の「う」を地声で出す
- 徐々に音を上げていき、地声の限界に近づいたら「い」に切り替える
- 「い」は裏声で発声する
👉 ポイント
切り替えの瞬間に声が弱くならないように意識しましょう。
裏声でも声を前に飛ばす気持ちを持つと、スムーズで安定した発声につながります。
② 身体を使って行う方法(「うーいー」+手の動き)
- 片手を下に置いた状態からスタート
- 「うー」 を発声しながら手を下から上へゆっくり持ち上げる(地声で低音から中音へ)
- 「いー」 に切り替えるタイミングで裏声へ移行
- 手が上に上がったときに、高音の裏声が響くイメージを持つ
👉 ポイント
手の動きと声をリンクさせると、切り替えの瞬間を身体でつかみやすくなります。
「声を上に運ぶ」感覚を養うことで、地声から裏声への移行が自然になります。
<アドバイス> どちらの練習でも「青空に声を届けるように」リラックスして伸ばすことが大切です。
💡 慣れてきたら
ピアノや音源に合わせて音程を少しずつ上げ下げしてみましょう。
音階練習を取り入れることで、地声から裏声までの移行がよりスムーズになり、安定した発声につながります。。
裏声を取り入れるメリット
裏声(ファルセット)では輪状甲状筋が強く働くため、この筋肉を効率的に鍛えることができます。
普段から裏声を使う習慣がない方は、練習に少し取り入れるだけでも高音域が安定しやすくなります。
また、音階をスライドしながら裏声と地声を行き来する練習もおすすめです。声帯の長さや張力の変化をスムーズにし、より自然に高音へ移行できるようになります。
高音だけでなく低音も大切
高音の筋肉があるように、低音を支える筋肉も存在します。
ピアノの音階に合わせて低音から高音まで発声することで、喉周りの筋肉全体をバランスよく鍛えることができます。
💡 特に、甲状披裂筋(TA:Thyro-arytenoid muscle)と輪状甲状筋(CT:CrycoThyroid muscle)のバランスが整うと、いわゆる「ミックスボイス」や滑らかな声域移動につながります。
発声で注意すべきポイント
- 無理に高音を張り上げると、喉を痛める原因になります。
- 喉がかすれる・痛む場合はすぐに休むことが大切です。
- 発声前のウォームアップ(ハミング・リップロールなど)で声帯を準備しましょう。
- 部屋の乾燥を防ぎ、水分補給をこまめに行うことも喉のケアには効果的です。
まとめ
- 高音発声には 輪状甲状筋 が重要
- 筋肉は使わないと衰える → 高音も出にくくなる
- 裏声練習で輪状甲状筋を効果的に鍛えられる
- 健康や嚥下機能の維持にも「声を出すこと」は役立つ
- 無理なく日常的に発声練習を取り入れることが大切
「きれいな高音が出ないから」と避けるのではなく、少しずつでも声を出す習慣をつけることで、歌声も健康も守ることができます。
📺 実際の発声イメージや練習はYouTube動画でも紹介していますので、動画とあわせてトライしてみてください。
動画が参考になった!という方は、ぜひ「いいね」や「チャンネル登録」をお願いします♪
今後の動画制作の励みになります(^-^)
📺 YouTube・Voice Office Tokyoチャンネルのご紹介
カバー曲やオリジナル楽曲、
そしてボイストレーニングや歌の上達に役立つ動画をYouTubeで配信しています。
チャンネル登録&高評価も、ぜひよろしくお願いします♪
皆さんの声がもっと自由に、もっと楽しくなるようなお手伝いができたら嬉しいです。
▼こちらをクリック▼
https://www.youtube.com/c/VoiceOfficeTokyo
📢 Instagramで 最新のボイトレ豆知識を発信
2025年からInstagramを開設しました。自宅でできるボイストレーニングや声の豆知識など、発声に役立つ情報をお届けしています。スキマ時間に活用できる内容が盛り沢山ですので、ぜひフォローしていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします♪
▼📸 こちらをクリック▼
Instagram
本格的に声について学びたい方へ
Voice Office Tokyoでは、初心者から上級者まで一人ひとりに合ったレッスンを提供しています。 滑舌改善や高音の出し方、歌唱力アップ、ボイストレーナーとしての知識を学びたいなど、あなたの目標に寄り添いながら具体的なスキルを磨けるカリキュラムをご用意しています。
詳しくはこちらからチェックしてください▼